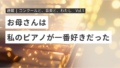自分にはもう伸びしろがない、と思っていた頃
高校生の頃、私はずっと思っていた。
自分は、もうこれ以上、上手くならないのだろうな、と。
手は小さく、オクターヴはギリギリ。
指も、決して速く回るほうではなかった。
当時の先生に、こんなふうに言われたことがある。
「希美子ちゃんは、手が小さいからね。指が速く回るわけでもないし。」
今思うと、これは絶対に言ってはいけない言葉だったとわかる。
この一言は、才能や能力以前に、人の中に強いブロックを作ってしまう。
特に、生まれ持った身体的な特徴は、努力でどうにもならないものだと受け取られやすい。
それは簡単に、「どうせ無理だ」という絶望に変わってしまう。
しかも、クラシック音楽の世界は、いわゆる“天才”と呼ばれる人たち、恵まれた身体能力を持った人たちが、人一倍の努力を重ねている世界だ。
自分は、どう頑張っても、そこには行けない…。
その結果、私は「無欲」になった。
ただし、それは健やかな無欲ではなく、あきらめに近い無欲だった。
「どうせ無理」
「もう天井が見えている」
そんな気持ちが、音楽への向き合い方を、どこか曇らせていた。
大人になってから、再びコンクールに向き合うようになった。
その頃には、コンクールはずいぶん増えていて、受賞歴がプロフィールに並ぶ時代になっていた。
正直に言えば、賞が欲しかった。
でも、なぜ欲しかったのかは、はっきりとはわからない。
受賞歴がある人が、少しうらやましかったのかもしれない。
プロフィールに書ける「何か」が、欲しかったのかもしれない。
転機になったのは、
あるコンクールで「特別賞」をいただいたことだった。
順位として、はっきりとした数字がつくわけではない。
けれど、「評価された」という事実だけは、確かにそこにあった。
そのとき、ふと、こんな気持ちが湧いた。
あれ?
私にも、受賞できる可能性があったんだ。
それまで眠っていた欲が、静かに目を覚ました瞬間だった。
私は、一度ちゃんとやってみよう、と思った。
受賞するためだけではないけれど、受賞を目指して、本気で向き合ってみようと。
ちょうどその頃、コンクールに対して、極端な否定をしない師匠のもとに通っていたことも、背中を押してくれた。
ただし、ひとつだけ、絶対に守ろうと決めていたことがあった。
「自分の演奏をする」
受賞を狙った演奏は、しない。
結果を気にしなかった、と言えば嘘になる。
でも、
評価のために音楽をねじ曲げることだけは、
したくなかった。
今振り返ると、
この時期は、
音楽における「評価」というものを、
初めて真剣に考え始めた時間だったと思う。
評価のための音楽は、違う。
でも、評価されたい。
この二つの気持ちは、当時の私の中で、ずっと同時に存在していた。
どちらかが正しいとも、どちらかが間違っているとも、まだ言えなかった。
ただ、その間で揺れながら、私は音楽と向き合っていた。
次回は、「自分の演奏をする」と決めたその先で、
思いがけず評価がついてきた体験と、そこから見えた景色について書こうと思う。