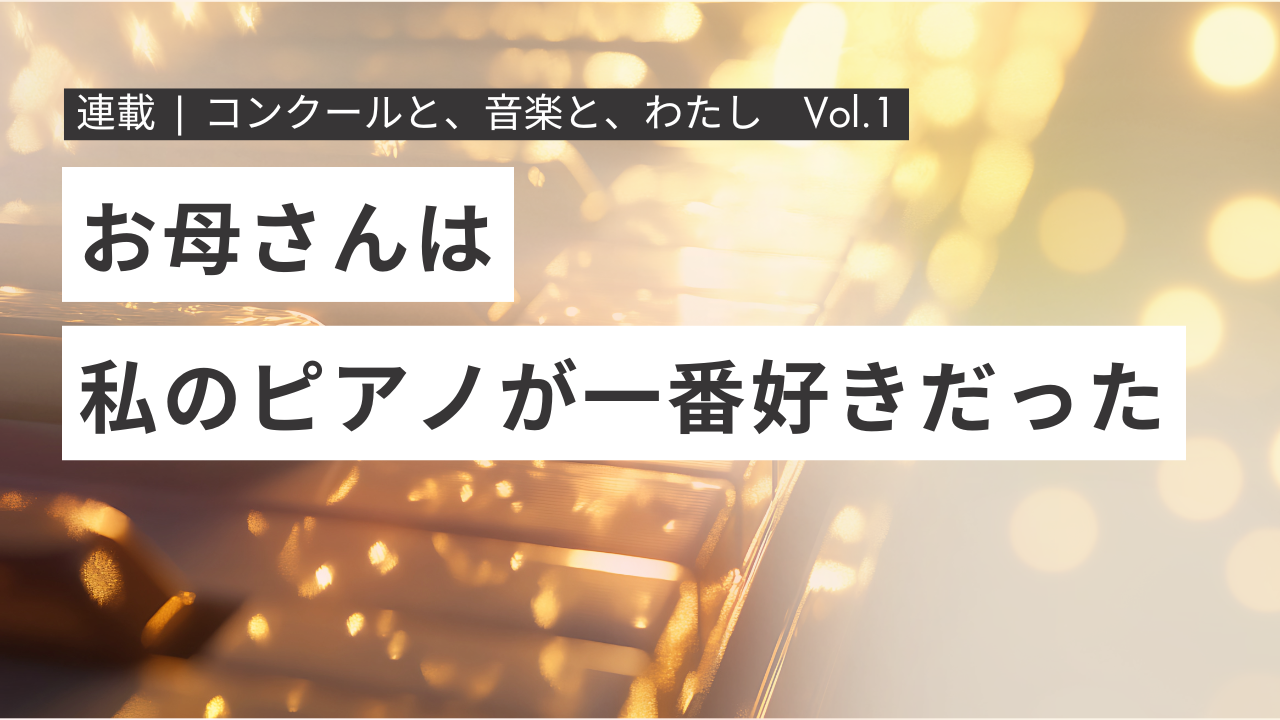お母さんは、私のピアノが一番好きだった
コンクールというものが、まだ特別だった頃
私が初めてコンクールを受けたのは、小学校5年生か6年生の頃だったと思う。
今のようにコンクールが乱立している時代ではなく、「コンクールに出る」というだけで、どこか特別な響きがあった。
だからといって、私は血眼になって練習するような子どもではなかった。
もともと欲があまりなく、「賞を取りたい」「勝ちたい」という気持ちも、ほとんどなかった。
それが良かったのかどうかは、正直、今でもわからない。
うちの親は、いわゆる“教育熱心”なタイプではなかった。
というより、私に対して過度な期待を、まったくしていなかった。
受賞できても、できなくても、本当にどうでもいいと思っていたのだと思う。
コンクールの日も、「がんばってね」と言われた記憶はない。
会場へ行って、帰りに、年に1~2回しか連れて行ってもらえない喫茶店に寄って、それで終わり。
とても淡々とした一日だった。
ただ、ひとつだけ、今でもはっきり覚えている場面がある。
受賞できなかった帰り道、母がふと、こう言った。
「お母さんは、希美子の演奏が一番好き。希美子のピアノが、一番上手く聴こえる。」
親バカだな、と思う。
でも、あれはきっと、本音だった。
その言葉を聞いたとき、私はとても救われた気持ちになった。
「お母さんが私の演奏が好きなら、まいっか」
それだけで、十分だった。
今思えば、私はとても早い段階で、“評価とは別の場所にある安心感”を知っていたのかもしれない。
音楽をやめなくていい理由。
続けていていい理由。
それが、順位や賞ではなく、
「誰かが、あなたの音を好きだと言ってくれること」
だったということ。
これは余談だけれど、思春期になって自分の顔にコンプレックスを感じ始めた頃も、母は同じことをしていた。
「希美子はかわいい」
「目が大きくてかわいい」
それを、何度も、何度も言う。
不思議なもので、ずっと言われ続けていると、
「まぁ、確かに目は大きいな」
「自分で思うほど、ひどくはないかも」
と思えてくる。
人は、自分の価値を、誰の言葉で受け取るかによって、見えてくる世界が変わるのだと思う。
コンクールは、評価される場所だ。
でも、音楽を続ける理由は、評価とは別のところにあっていい。
このあと私は、自分の限界を感じたり、賞が欲しくなったり、評価に振り回されたりもする。
けれど、この最初の体験が、ずっと私のどこかで、静かに支え続けてくれていた。
そんなことを、審査員という立場になった今、あらためて思い出している。
次回は、「自分にはもう伸びしろがない」と思い込んでいた高校時代の話を書こうと思う。