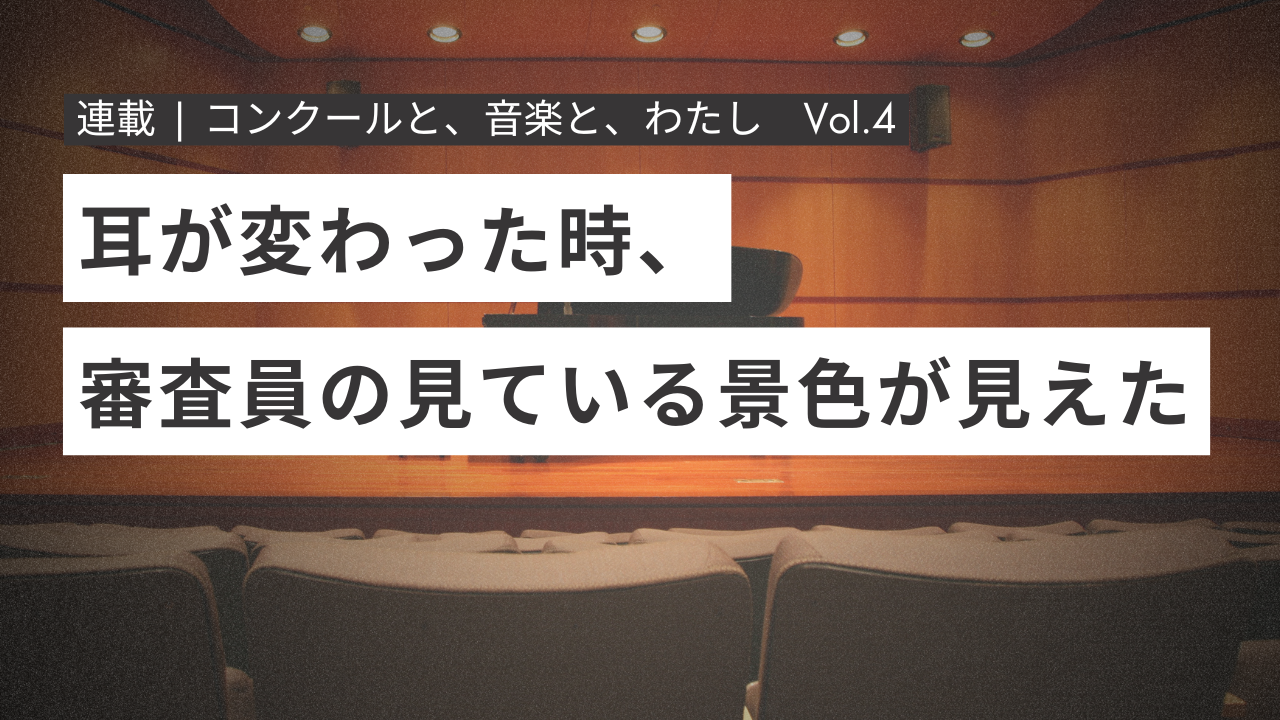耳が変わったとき、審査員の見ている景色が見えた
今の師匠のもとで学び始めてから、私は本当の意味で、0からのスタートを切った。
これまで積み上げてきた奏法は、一度、すべて横に置く。
音の出し方も、身体の使い方も、「正しい」と信じてきた感覚さえも、いったん疑うところから始まった。
正直、楽な道ではなかった。
でもそれ以上に、長年、無意識に感じていた違和感や不快感が、次々と解明され、解放されていくことが、楽しくて仕方がなかった。
数年が経った頃、ふと、こんな疑問が湧いた。
この奏法は、舞台でどう響くのだろう。
自分の部屋で弾いているときと、ホールで音が立ち上がるとき。
その違いを、確かめてみたくなった。
それで私は、再びコンクールに出始めた。
今度は、「評価を取りに行く」ためではない。
この音が、どう聴こえるのか。
それを知るためだった。
その頃から、私は自分の中で、ある変化に気づくようになった。
講評の受け取り方が、以前とはまったく違っていたのだ。
以前は、一言一句を気にして、落ち込んだり、舞い上がったりしていた。
でも、その頃の私は、講評を読みながら、こう思っている自分に気づいた。
あ、この先生は、ここを聴いている。
この人は、ここまでは聴いていない。
音色。
響き。
倍音。
それらを聴き取れる耳を持つ審査員と、そうではない審査員がいる。
後者の場合、評価の基準は、どうしても音量や速度、わかりやすいメリハリに寄っていく。
それが良い、悪いではない。
ただ、聴いている世界が違うのだ。
本気で自己鍛錬を続けていると、不思議なことが起こる。
審査される側が、審査する側の耳を“感じ取れる”ようになる。
この人は、どこまで聴いているのか。
何を音楽だと感じているのか。
それが、講評ではっきりと伝わってくる。
その頃から、私は、コンクールの結果に一喜一憂しなくなった。
「結果は、審査員次第」
これは、投げやりな諦めではない。
前提としての事実だ。
誰に評価されるのか。
その耳が、どこまでの世界を聴いているのか。
それによって、結果は大きく変わる。
やがて、私にも審査員の声がかかるようになった。
いざ審査席に座ってみると、思ってもみなかった現実があった。
本当に良いものを持っているのに、落とさなければならないケースが、確かに存在するのだ。
信じられなかった。
でも、その日の演奏、その場の基準で、点数をつけなければならない。
そのとき、私の頭をよぎったのは、演奏そのものよりも、その先の人生だった。
この結果ひとつで、
「もうピアノはやめよう」
「もうやめさせよう」
そう決めてしまう人が、どれだけいるのだろう。
実際、私の生徒の中にも、親御さんにこう言われたことがある。
「これだけコンクールで賞が取れないなら、才能がないのだと思います。」
その考えを覆すのは、簡単なことではなかった。
だから私は、講評の書き方を、意識的に変えている。
よくある
「メロディーと伴奏のバランスが」
「もっと抑揚を」
「感情を込めて」
そういった言葉は、あえて書かない。
特に、才能があるのに、点数を低くつけざるを得なかった人には、私は、こんなことを書くようにしている。
今は、弱点だと思っているその部分が、これから先、武器になる可能性があること。
コンクールでは、評価されにくいかもしれないけれど、そういう要素こそが、聴く人の心に残るということ。
今回のコンクールで1位は取れなくても、お金を払ってでも、もう一度聴きたいと思われる演奏は、今日のあなたのような音楽だということ。
正直に言えば、講評を書いたあと、さらにフォローアップしたいくらいだ。
短時間で、限られた文字数で、すべてを伝えることには、どうしても限界がある。
なぜ、その講評になったのか。
どこを聴いていたのか。
本当は、解説までしたい。
次回は、審査員という立場から見えてきた「コンクールの本当の役割」と、それでもなお、コンクールを受ける意味があるとしたら何か、そのことについて書こうと思う。